自動車と原動機(エンジン)/電動機(モーター)に打刻を行う必要がある。
仮に原動機(エンジン)/電動機(モーター)が2つや3つある場合には、その説明をする必要がある。
申請に先んじて、打刻届出が必要(型式指定や輸入車特別取扱制度(PHP)の届出時でもOK)。並行輸入で打刻がない車両については、運輸支局で職権打刻をしてもらうこともある。
打刻届出に提出するものは、施行規則にて定められているものの、輸入車であれば製作者の証明や車台番号(Vehicle Identified Number)の各々の桁の説明を求められる。
修正打刻についても予め提出することが可能。
車検時や審査時に、実際に確認される。また字体まで確認しているとされる。電動機についてはラベルを貼付することにより、車検時の確認等を代表できるように通達の改正がなされている。
適当でない打刻については解説に記載があり、
- 既にあるものと同じ様式、車台の型式を表示する文字がない、MOTASに登録できない(17桁以下にすること)。
- 改造や修理の際に交換されやすい部分、視認が困難(車検状等では、ファイバースコープを使用してもOK。結構日本独自のため、海外メーカに依頼をするのが難しい。)、損傷、摩耗または腐食しやすい
- 打刻が容易に塗沫できる。直接打刻されていない
などで撥ねられる要素がある。
車台番号はWMI (World Manufacturer Identification)で定められることが多いです。また、USの法規で、外から車台番号が見えるようになっていますが、これは日本で言う打刻ではない。
字体の提出は、届出書に実際の大きさで提出が必要だったと思いますが、設計図でも問題なかったと思います。
完成検査の監査時に、完成検査の打刻の確認方法、判別方法、失敗した際の取り扱いを聞かれることがある。
US産の車両について打刻が乱れていることがよくあった。その際にどこまで問題ないと認められるかは、検査官次第のところもあるので、事前に調整が必要。
法
第二十九条自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外の者は、自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻してはならない。
2自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び前項の指定を受けた者が自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻しようとするときは、その様式その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。
3国土交通大臣は、前項の届出に係る事項が適当でないと認めるときは、その変更を命ずることができる。
施行規則
(打刻の届出事項)
第二十六条の七 法第二十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 打刻様式
二 打刻字体
三 打刻位置
(打刻の届出)
第二十七条 法第二十九条第二項の届出は、第六号様式により自動車の車台又は原動機の型式ごとに行わなければならない。
2 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、前項の届出をする者に対し、自動車、自動車の車台又は原動機の製作を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。
自動車認証実施要領 附則2 自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻届出等取扱要領
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20240110/3_20240105_buturyuzidousya03.pdf
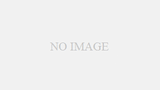
コメント