法 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185#Mp-Ch_3-At_40
(共通構造部の指定)
第七十五条の二国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、車枠又は車体及びその他の第四十一条第一項各号に掲げる装置の一部から構成される自動車の構造部分であつて、複数の型式の自動車に共通して使用されるもの(以下この条において「共通構造部」という。)のうち、当該共通構造部により当該共通構造部を有する自動車の第四十条第八号に掲げる事項が特定されることとなるもの(-> 最小回転半径)(以下「特定共通構造部」という。)をその型式について指定する。
2前項の規定による指定の申請は、本邦に輸出される特定共通構造部について、外国において当該特定共通構造部を製作することを業とする者又はその者から当該特定共通構造部を購入する契約を締結している者であつて当該特定共通構造部を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
3第一項の規定による指定は、申請に係る特定共通構造部の当該申請に係る構造、装置及び性能が保安基準に適合し、かつ、当該特定共通構造部が均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。この場合において、次条第一項の規定によりその型式について指定を受けた装置は、保安基準に適合しているものとみなす。
4国土交通大臣は、第一項の申請をした者が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(同項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、同項の規定による指定の効力を停止することができる。この場合において、国土交通大臣は、指定の効力を停止するときは、当該停止の日までに製作された共通構造部について当該停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。
5国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定による指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された共通構造部について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
一その型式について指定を受けた特定共通構造部の当該指定に係る構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなつたとき。
二その型式について指定を受けた特定共通構造部が均一性を有するものでなくなつたとき。
三不正の手段によりその型式について指定を受けたとき。
6前項の規定によるほか、国土交通大臣は、指定外国共通構造部製作者等(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定共通構造部の型式について第一項の規定による指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国共通構造部製作者等に係る第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一指定外国共通構造部製作者等が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(第一項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
二国土交通大臣が第一条の目的を達成するため必要があると認めて指定外国共通構造部製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
三国土交通大臣が第一条の目的を達成するため特に必要があると認めてその職員に指定外国共通構造部製作者等の事務所その他の事業場又はその型式について指定を受けた特定共通構造部の所在すると認める場所において当該特定共通構造部、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
7特定共通構造部のうち国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところによりその型式について外国が行う第一項の規定による指定に相当する認定その他の証明を受けた場合には、前条第三項後段の規定の適用については、第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部とみなす。
(特定共通構造部及び特定装置の表示)
第七十五条の四第七十五条の二第一項又は前条第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた特定共通構造部又は特定装置につき、国土交通省令で定めるところにより、第七十五条の二第一項又は前条第一項の指定を受けたものであることを示す国土交通省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2何人も、前項に規定する場合を除くほか、特定共通構造部又は特定装置に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
3特定共通構造部又は特定装置を輸入することを業とする者は、第一項の規定により表示が付されている場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定共通構造部又は特定装置を輸入したときは、これを譲渡する時までにその表示を除去しなければならない。
(型式についての指定に係る独立行政法人自動車技術総合機構の審査)
第七十五条の五国土交通大臣は、第七十五条第一項に規定する自動車の型式についての指定、第七十五条の二第一項に規定する特定共通構造部の型式についての指定及び第七十五条の三第一項に規定する特定装置の型式についての指定に関する事務のうち、当該自動車及び当該特定共通構造部の構造、装置及び性能並びに当該特定装置が保安基準に適合するかどうかの審査を機構に行わせるものとする。
2機構は、前項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。
共通構造部型式指定規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000800015
(指定の申請)
第二条指定の申請は、特定共通構造部を製作することを業とする者若しくはその者から特定共通構造部を購入する契約を締結している者であって当該特定共通構造部を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される特定共通構造部を製作することを業とする者又はその者から当該特定共通構造部を購入する契約を締結している者であって当該特定共通構造部を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製作者等」という。)又は特定改造等を業とする者が、製作若しくは販売(以下「製作等」という。)をする特定共通構造部又は特定改造等に係る改造のためのプログラム等が組み込まれる装置を取り付ける特定共通構造部について行うものとする。
第三条指定を申請する者(以下「申請者」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定共通構造部を機構に提示しなければならない。
一特定共通構造部の名称及び型式
二車台の名称及び型式
三車体の名称及び型式
四申請者の氏名又は名称及び住所
五主たる製作工場の名称及び所在地
2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第四号、第五号、第七号及び第八号を除く。)を添付しなければならない。
一申請に係る特定共通構造部の構造、装置及び性能を記載した書面
二申請に係る特定共通構造部の外観図
三道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)の規定(申請に係る特定共通構造部が対象となる部分に限る。)に適合することを証する書面(法第七十五条の三第一項の規定による指定を受けた特定装置(以下「指定特定装置」という。)については、当該指定を受けたことを証する書面)
四品質管理システム(申請に係る特定共通構造部の品質管理の計画、実施、評価及び改善に関し、申請者が自らの組織の管理監督を行うための仕組みをいう。)に係る業務組織及び実施要領を記載した書面(申請者が国際標準化機構第九〇〇一号の規格により登録されている場合(申請に係る特定共通構造部に関し、前項第五号の主たる製作工場について登録されている場合に限る。)にあっては、登録されていることを証する書面)
五第七条第二項の検査に係る業務組織及び検査の実施要領を記載した書面(以下「検査実施要領」という。)
六製作者等が申請に係る特定共通構造部に法第七十五条の四第一項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
七前条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
八次の各号に掲げる処分を受け、かつ、当該処分を受けた日以後初めて指定の申請をする者にあっては、当該処分に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面
イ法第七十五条第七項の規定による同条第一項の規定により指定を受けた自動車(以下「指定自動車」という。)の型式についての指定の効力の停止
ロ法第七十五条第八項の規定による指定自動車の型式についての指定の取消し
ハ法第七十五条の二第四項の規定による指定を受けた特定共通構造部(以下「指定特定共通構造部」という。)の型式についての指定の効力の停止
ニ法第七十五条の二第五項の規定による指定特定共通構造部の型式についての指定の取消し
ホ法第七十五条の三第五項の規定による指定特定装置の型式についての指定の効力の停止
ヘ法第七十五条の三第六項の規定による指定特定装置の型式についての指定の取消し
3国土交通大臣又は機構は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074
(整備管理者の選任)
第三十一条の三 法第五十条第一項の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとし、同項の国土交通省令で定める台数は、当該各号に定める台数とする。
一 乗車定員十一人以上の自動車(次号に掲げる自動車を除く。) 一両
整備管理者の資格)
第三十一条の四 法第五十条第一項の自動車の点検及び整備に関する実務経験その他について国土交通省令で定める一定の要件は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第五十三条に規定する命令により解任され、解任の日から二年(前条第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、五年)を経過しない者でないこととする。
一 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して二年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。
二 自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。
三 前二号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。
(整備管理者の権限等)
第三十二条 法第五十条第二項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。
一 法第四十七条の二第一項及び第二項に規定する日常点検の実施方法を定めること。
二 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
三 法第四十八条第一項に規定する定期点検を実施すること。
四 第一号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。
五 第一号、第三号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。
六 第三号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。
七 法第四十九条第一項の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
八 自動車車庫を管理すること。
九 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。
2 整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。
第三十二条の二 削除
(整備管理者の選任届)
第三十三条 法第五十二条の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出者の氏名又は名称及び住所
二 届出者が自動車運送事業者であるかどうかの別
三 整備管理者の選任に係る自動車の使用の本拠の名称及び位置
四 第三十一条の三各号に掲げる自動車の数
五 整備管理者の氏名及び生年月日
六 第三十一条の四各号のうち前号の者が該当するもの
七 整備管理者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務内容)
2 前項の届出書には、同項第五号の者が同項第六号に掲げる者に該当すること及び法第五十三条に規定する命令により解任され、解任の日から二年(第三十一条の三第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、五年)を経過しない者でないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。
※整備管理者 (法)
第五十条自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。
2前項の規定により整備管理者を選任しなければならない者(以下「大型自動車使用者等」という。)は、整備管理者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。
第五十一条削除
(選任届)
第五十二条大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から十五日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様である。
(解任命令)
第五十三条地方運輸局長は、整備管理者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、大型自動車使用者等に対し、整備管理者の解任を命ずることができる
(出荷検査証の発行)
第六十二条の六 法第七十五条の二第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた特定共通構造部を有する特定共通構造部型式指定自動車を譲渡する場合には、当該特定共通構造部型式指定自動車が次に掲げる基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、出荷検査証を発行し、これを譲受人に交付することができる。
一 指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有すること。
二 道路運送車両の保安基準の規定(当該特定共通構造部が対象となる部分に限る。)に適合すること。
三 法第二十九条第二項又は法第三十条の届出をした車台番号及び原動機の型式が明確に打刻されていること。
2 前条第二項及び第三項の規定は、特定共通構造部型式指定自動車に係る前項の規定による出荷検査証の発行及び交付について準用する。
3 第一項の申請をした者は、同項の規定により出荷検査証を発行したときは、当該特定共通構造部型式指定自動車の点検整備方式(自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)第七条第三項及び第八条の技術上の情報を含む。)を使用者に対して周知させるための措置を講じなければならない。
自動車点検基準
別表第1(事業用自動車、自家用貨物自動車等の日常点検基準)(第一条関係)
点検箇所
点検内容
1 ブレーキ
1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの効きが十分であること。
2 ブレーキの液量が適当であること。
3 空気圧力の上がり具合が不良でないこと。
4 ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合にブレーキ・バルブからの排気音が正常であること。
5 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。
2 タイヤ
1 タイヤの空気圧が適当であること。
2 亀き裂及び損傷がないこと。
3 異状な摩耗がないこと。
(※1)4 溝の深さが十分であること。
(※2)5 ディスク・ホイールの取付状態が不良でないこと。
3 バッテリ
(※1) 液量が適当であること。
4 原動機
(※1)1 冷却水の量が適当であること。
(※1)2 ファン・ベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファン・ベルトに損傷がないこと。
(※1)3 エンジン・オイルの量が適当であること。
(※1)4 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。
(※1)5 低速及び加速の状態が適当であること。
5 灯火装置及び方向指示器
点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。
6 ウインド・ウォッシャ及びワイパー
(※1)1 ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。
(※1)2 ワイパーの払拭しよく状態が不良でないこと。
7 エア・タンク
エア・タンクに凝水がないこと。
8 運行において異状が認められた箇所
当該箇所に異状がないこと。
(注)
①(※1)印の点検は、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。
②(※2)印の点検は、車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車に限る。
第四章 道路運送車両の点検及び整備
(使用者の点検及び整備の義務)
第四十七条自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
(日常点検整備)
第四十七条の二自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
2次条第一項第一号及び第二号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、一日一回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。
3自動車の使用者は、前二項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。
(定期点検整備)
第四十八条自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
一自動車運送事業の用に供する自動車及び車両総重量八トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車三月
二道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)、同法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車(前号に掲げる自家用自動車を除く。)六月
三前二号に掲げる自動車以外の自動車一年
2前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
共通構造部 通達 https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20240110/15_20240105_buturyuzidousya15.pdf
第3 申請書及び添付書面
1 型式指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国土交通大臣に対し、
共通構造部指定規則第1号様式による共通構造部型式指定申請書及び別表に掲げる添付
書面を提出すること。また、研究所に第1号様式の写し及び添付書面を提出すること。
なお、申請書の添付書面は、別表左欄に掲げるとおりとし、その記載要領等は、同表
右欄に掲げるとおりとする。
2 申請書の記載に際しては、次の点に留意すること。
主たる製作工場の名称及び所在地欄には、原動機、車台及び多仕様自動車について、
それぞれの製作工場の名称及び所在地を記載すること。
第4 点検整備方式の周知
施行規則第62条の6第3項の「当該特定共通構造部型式指定自動車の点検整備方式
(自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第7条第3項及び第8条の技術上の情報
を含む。)を使用者に対して周知させるための措置」とは、次のいずれかのことをい
う。
1 (1) 第1次使用者に対しては、点検整備方式を記載した書面を販売の際に交付するこ
と。
(2) 第2次以降の使用者に対しては、 (1)の書面を常時準備しておき、これを提供し
得る体制を整えておくよう努めること。
2 (1) 点検整備方式を電磁的方法により常に提供可能な体制を整えること。
(2) 第1次使用者に対しては、販売の際に (1)による提供であることを周知するこ
と。
(3) 第2次以降の使用者に対しては、 (1)による提供であることを周知し得る体制を
整えておくよう努めること。
(4) 上記の他、使用者が希望する場合にあっては書面での提供をし得る体制を整える
こと。
2 出荷検査の実施にあたっては、次の点に留意すること。
(1) 統計的手法を用いる出荷検査を実施する場合にあっては、その方式が明確にされ
ていること。
(2) 出荷検査に従事する者は、当該検査に必要な知識及び技能を有する者であるこ
と。
(3) 出荷検査の一部を委託するときは、次に掲げる要件が満たされていること。
(ア) 委託している業務の範囲が明確であり、かつ、委託先の業務の実施体制が確立
されていること。
(イ) 多仕様自動車の引取りの際の抜取検査の実施等委託している業務に関する指導
監督の徹底が図られていること。
(4) 自動車検査用機械器具により自動で出荷検査を実施するときは、自動車検査用機械
器具の性能及びその管理の方法に関し、次に掲げる要件が満たされていること。な
お、本項に定めのない事項は、完成検査の自動化ガイドライン(令和3年3月)又
はこれに準じた方法によるものとする。
(ア) 当該自動車検査用機械器具を用いて実施される出荷検査の項目について、出荷検
査に従事する者と同等以上の精度で判定すること。
(イ) 当該自動車検査用機械器具の異常を自動的に検知し、当該器具を停止させ、か
つ、当該異常の結果を記録すること。
(ウ) 当該自動車検査用機械器具を用いて実施された出荷検査の結果について自動で記
録し、また不正な書き換えをできないようにする措置を講じていること。
(エ) 当該自動車検査用機械器具の適確な運用に関する知識及び能力を有する者から管
理責任者が明確に定められていること。
(オ) 当該自動車検査用機械器具の管理要領が明確に定められていること
3 製作者等は、当該多仕様自動車についての出荷検査を行ったときは、当該検査の成績
を記録し、これを1年間保存すること。
4 施行規則第62条の6第1項の特定共通構造部型式指定自動車出荷検査証(以下「出荷
検査証」という。)の様式は、第3号様式によること。なお、出荷検査証に記載すべき
事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供する場合には、当該登録情報処理機関
が定める要領に基づき作成すること。
また、当分の間、施行規則第62条の5に基づく「排出ガス検査終了証(認証実施要領
附則15第1号様式)」の備考欄に「特定共通構造部型式指定番号」及び「類別区分番
号」を記載することにより、出荷検査証とすることができる。
5 誤記等の瑕疵がある出荷検査証を発行した場合には、製作者等は、速やかにその概要
を国土交通省物流・自動車局審査・リコール課長に報告するとともに、その指示に従っ
て適切な措置を行うとともに、誤発行の原因を究明して同種の誤発行の再発を防止する
ための対策を行うこと。
第13 出荷検査証の発行の記録及び保存
1 指定製作者等は、出荷検査証を発行したときは、当該特定共通構造部型式指定自動車
に係る次に掲げる(1)又は(2)の書類を作成し、保存することにより行うこと。ただし、
別紙3「電子情報処理組織による出荷検査証の発行記録取扱方法」によって記録しても
よい。
(1) 出荷検査証の写し
(2) 出荷検査証に記載した特定共通構造部の型式指定番号、多仕様自動車番号、類別区
分番号、車台番号、発行年月日等を記録した書類
2 施行規則第62条の6第1項の特定共通構造部型式指定自動車出荷検査証(以下この項
において「紙発行された出荷検査証」という。)に記載されている事項を電磁的方法に
より登録情報処理機関に提供する場合には、その記録も併せて保存すること。
なお、紙発行された出荷検査証の記載事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提
供した場合には、当該紙発行された出荷検査証を1年間保存すること。
| 提 出 す る 場 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 型式指定を受けた場合 | 既指定共通構造部型式指定を受けた場合 | 第5 第2項に係る変更の届出をした場合 | 共通構造部指定規則第8条第1項第2号の軽微な変更の届出をした場合 | ||
| 提出資料 | 諸元表 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外観図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 走行性能曲線図 | ○ | ○ | |||
| 構造・装置の概要説明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 指定装置等又は指定共通構造部一覧表 | ○ | ○ | ○ | ||
| 添 付 資 料 | 記 載 要 領 等 | |
| 1 | 提出書面一覧表 | 記載要領は、附則2「共通構造部(多仕様自動車)型式指定申請書等提出要領」によること。 |
| 2 | 多仕様自動車の範囲 | 多仕様自動車の範囲については別記様式によること。 |
| 3 | 多仕様自動車の構造、装置及び性能を記載した書面 (以下「諸元表」という。) | 諸元表の様式は第1号様式及び第2号様式によること。なお、該当しない欄を削除することができる。 記載要領は、附則4「共通構造部(多仕様自動車)の諸元表の記載要領」によること。 諸元表は車名及び検査・登録時に使用する (自動車検査証に記載される)型式(以下 「検査・登録型式」という。)毎に作成すること。 |
| 4 | 外観図及び外観写真 | 外観図の記載は、附則6「共通構造部(多仕 様自動車)の外観図の記載要領」によること。 研究所で審査を実施しない協定規則第 48 号の技術的な要件に係る灯火装置の取付位置及び多仕様自動車の範囲に含まれない部位の寸法の記載は要しないものとする。 外観写真は、少なくとも、多仕様自動車の斜め前、斜め後ろから撮影し、多仕様自動車の外観を判別できるものであること。ただし、エンブレム、バッジ、エアスポイラー等の装飾物及び新規検査若しくは予備検査を受けようとする際に取付方法が同一でないものが含まれていなくともよい。 |
| 5 | 保安基準の規定に適合することを証する書面 | |
| (1) | 走行性能曲線図(けん引自動車に係るものに限る。) | 道路勾配(正接で表示する。)が0、3、 5、10、10 以上は5きざみの各パーセントである場合の走行抵抗を表示すること。 タイヤの半径は動荷重半径とすること。ただ し、動荷重半径が「自動車用タイヤの取扱い について」(昭和57年6月28日自車第502号) による日本自動車タイヤ協会規格(以下 「JATMA 規格」という。)に定められていないタイヤについては、静荷重半径等とすること。 |
| (2) | 原動機性能曲線図 ( WHTCモード及びWHSCモー ド、JE05モード、ガソリン7モード、ディーゼル8モード及びNRTCモード排出ガス試験の適用を受ける多仕 様自動車に係るものに限る。) | 全負荷時の出力及びトルクを記載すること。 |
| (3) | 運転者席付近配置図 | 保安基準第10 条第1項各号に掲げる装置、かじ取装置等の名称及び位置を記載すること。 |
| (4) | 指定装置等又は指定共通構造部 | 装置指定通知書等、共通構造部指定通知書等又は認定証の写しを添付するとともに指定装置等又は指定共通構造部一覧表を添付すること。 |
| (5) | 車わく強度計算書(最大積載量を有する自動車及び乗 合自動車に係るものに限る。) | 強度計算は、公益社団法人自動車技術会が定めた自動車負荷計算基準又は多仕様自動車製作者が定めた計算基準に基づいて行うこと。なお、ストレンゲージ等による測定成績書をもって強度計算書に代えることができる。 |
| (6) | 次に掲げる装置等の図面 | 1 平面図及び側面透視図又は鳥かん透視図若しくは装置等の外観写真をもって(ア)~(キ)までに掲げる装置等の図面(液化石油ガス(以下「LPG」という。)、圧縮天然ガス(以下「CNG」という。)又は液化天然ガス(以下 「LNG」という。)を燃料とする多仕様自 |
| 動車及び圧縮水素ガスを燃料とする多仕様自動車に係る燃料装置の図面を除く。)の全部に代えることができる。 2 二輪自動車にあっては、(ア)から(キ)までに掲げる装置等が明示された図面であれば、項目ごとに別葉とする必要はない。 | ||
| シャシ全体図 燃料装置 動力伝達装置 走行装置 かじ取装置 制動装置 緩衝装置 灯火装置(二輪自動車に係るものを除く。) | 排気管、ブレーキ管及び燃料管の配置についても記載すること。 燃料系統の組立及び配管を記載すること。LPG、 CNG又はLNGを燃料とする多仕様自動車及び圧縮水素ガスを燃料とする多仕様自動車にあって は、容器格納室、容器取付関係及び充填口付近についても記載すること。 車軸についても記載すること。 制動系統の組立及び配管を記載すること。 灯火の外形等を記載すること。 | |
| (7) | 検討書 | 保安基準の規定に適合しているかどうかを検討した結果を記載すること。 なお、指定装置等及び指定共通構造部については検討した結果を省略することができる。 |
| 6 | 構造・装置の概要説明書 | 多仕様自動車の構造・装置の特徴を中心として記載すること。 |
| 7 | その他多仕様自動車の構 造・装置及び性能に関して必要な書面 | |
| (1) | けん引自動車以外の自動車に係るものにあっては走行性能曲線図(必要があると認められる場合に限る。) | 道路勾配(正接で表示する。)が0、3、 5、10、10 以上は5きざみの各パーセントである場合の走行抵抗を表示すること。 タイヤ半径は動荷重半径とすること。ただし、動荷重がJATMA 規格に定められていないタイヤについては、静荷重半径等とすること |
| (2) | WHTC モード及びWHSC モー | 全負荷時の出力及びトルクを記載すること。 |
| ド、JE05 モード、ガソリン 7モード、ディーゼル8モード及びNRTCモード排出ガス試験の適用を受ける多仕様自動車以外の多仕様自動車に係るものにあっては原動機性能曲線図(必要があ ると認められる場合に限る。) | ||
| (3) | その他審査の実施に当たって必要があると認められる書面 | |
| 8 | 多仕様自動車の出荷検査の実施要領を記載した書面 (申請に係る多仕様自動車の共通構造部指定規則第3条第2項第5号の検査実施 要領を記載した書面含む。) | 車名及び検査・登録型式毎に次に掲げる事項を記載すること。 申請に係る多仕様自動車の共通構造部指定規則第3条第2項第5号の検査実施要領 検査の業務組織 検査の実施要領 検査の実施項目 検査の実施方法 検査の実施方式 第12第2項(4)の自動車検査用機械器具により自動で出荷検査を実施する場合にあっては、当該業務を行う組織、検査の実施項目及び方法 出荷検査ラインの工程 出荷検査チェック・シート 出荷検査用機械器具の一覧表なお、第12第2項(4)の自動車検査用機械器具により自動で出荷検査を実施する場合にあっては、その旨を附記すること。 第12第2項(3)により出荷検査の一部を委託する場合における委託先、委託している業務の範囲、委託先の業務の実施体制及び委託している業務に関する指導監督の方法 1から5までに掲げる事項に係る変更の管理に |
| 関する手順を提出することができる。 | ||
| 9 | 特定共通構造部型式指定自動車出荷検査証の発行要領を記載した書面 | 出荷検査証の発行における業務分担が明確となるよう記載すること。 |
| 10 | 申請に係る多仕様自動車の品質管理システムに係る業務組織及び実施要領を記載した書面(申請者がISO第 9001 号等を取得している場合(申請に係る多仕様自動車に関し、主たる製作工場について取得している場合に限る。)にあっては、取得している事実を証する書面に代えことができる。こ の場合において、EN (European Norm)ISO9 001、JIS(日本産業規格)Q9001又はIATF16949の各規格はISO9001と同等以上の規格の例とする。 ) | 次に掲げる事項を記載すること。 品質管理システムに係る業務組織 申請に係る特定共通構造部の品質管理システムに係る実施要領として、次に掲げる事項を規定した規程類の名称を記載すること。 品質管理システムの方針及び目標 品質管理システムに係る計画 品質管理システムに係る評価の方法 継続的改善並びに是正措置及び予防措置 (不具合情報の収集・分析、当該情報を踏まえた対応を含む。) ISO 第9001 号等を取得している事実を証する書面に代える場合は、取得証明書(写し)を添付すること。 |
| 11 | 点検整備方式を記載した書面 | 点検整備方式(自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第7条第3項に定める技術上の情報に関するものに限る。)の書面については、当該情報の掲載場所等を記載すること。 点検整備方式(自動車点検基準第7条第3項に定める技術上の情報に関するものを除く。)の書面の記載については、次の点に留意すること。 自動車点検基準に定める技術上の基準を満足するものであること。 自動車点検基準に定めていない技術上の基準についても必要に応じ記載すること。 点検整備の際の判定基準について記載すること。特に、品質、形状等が変化し、通常の |
| 点検ではその後の保安を確保しうる期間を予測しにくい部品については、定期交換時期を記載すること。 3 前項(2)及び(3)については、製作者等が自動車の使用者に対し、標準として推奨するものである旨記載すること。 | ||
| 12 | 特定共通構造部型式指定番号等表示図 | 型式指定番号等を表示する場合、表示位置、表示方式を記載すること。 なお、上記第4項に掲げる図面に当該事項が記載されている場合には、提出を省略することができる。 |
| 13 | 申請者が多仕様自動車の販売を業とする者(本邦に輸出するものを含む。)である場合は、多仕様自動車の製作を業とする者との間に取り交わした契約書の写し | 契約書が日本語で記載されているもの以外のものにあっては、これを翻訳した書面を添付すること。 申請に係る多仕様自動車に関して、必要な技術情報の提供及び補修用部品の供給が当該多仕様自動車の製作を業とする者から申請者に対してなされる旨の契約が締結されることが、当該契約書等から明らかであること。 |
| 14 | 共通構造部指定規則第3条第2項第8号に該当する者にあっては、不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面 | 次に掲げる事項を記載すること。 不正行為の全容 不正行為の再発を防止するための組織体制の見直しを含めた具体的な措置 |
| 15 | 不正行為に係る部品について改善措置が適切に講じられていること及び改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面 | 次に掲げる事項を記載すること。 当該不正行為に係る部品について講じられた改善措置の内容及び申請に係る多仕様自動車に使用されている部品のうち当該不正行為に係る部品と同種のものについても、これと同様の措置が講じられており、問題が解消されていること。 当該不正行為が発生した理由(具体的事実に基づく説明)及び不正行為の再発を防止するための措置 |
| 備考1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。ただし、この大きさによる | ||
| ことが困難なものについては、折りたたんだ状態でこの大きさとする。 第9に掲げる提出書面を除き、既に同一の書面を提出しているときは、その旨を申し出ることによって当該書面の提出を省略することができる。 同時に複数の型式を申請する場合で同一の書面を提出するときは、その旨を申し出ることによって当該書面の提出を代表で提出することができる。ただし、代表で提出した場合であっても型式毎に第9の書面は提出するものとする。 添付書面については、申請に係る特定共通構造部の対象となる部分に限る。 | ||
別紙3(第13 関係)
電子情報処理組織による出荷検査証の発行記録取扱方法
- 記録
電子情報処理組織のファイル(以下「ファイル」という。)には、出荷検査証の発行と同時に、又は発行後速やかに出荷検査証の記載事項の全部を記録すること。
- 保管
ファイルは、検査主任技術者の責任の下に適切に保管すること。
- 検索
- 出荷検査証の記載事項についての検索の実施体制は、他の業務に優先して速やかに実施できるよう整備されていること。この場合において、「検索」とは、ファイル
から必要とする出荷検査証の記載事項の全部を抽出し、用紙に印字させることをいう。((2)において同じ。)
- 検索は、車台番号又は出荷検査証の証明番号により行うことができること。
- 関係規定の整備
出荷検査証の発行の事実の記録を本要領により行う場合には、別表(申請書の添付書面及びその記載要領等)第9項の特定共通構造部型式指定自動車出荷検査証の発行要領を記載した書面に、本要領の内容を明示しておくこと。第1号様式(諸元表例)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)
特定共通構造部の名称及び型式諸 元 表
| 1.特定共通構造部型式指定番号 | 12.類別区分番号 | |||
| 13.仕様 | ||||
| 2.特定共通構造部型式指定年月日 | 14.通称名 | |||
| 15.用途 | ||||
| 3.既指定共通構造部型式指定年月日 | 16.軸距 (m) | |||
| 17.車両最 大寸法 (m) | 17.1.長さ | |||
| 4.1.多仕様自動車番号 | 17.2. 幅 | |||
| 18.乗車定員(人) | ||||
| 4.2.車名及び型式 | ||||
| 5.車台の名称及び型式 | 19.最大積載量 (kg) | |||
| 20.最小車両重量 (kg) | ||||
| 6.製作者等の氏名又は名称 | 21.許容 限度(kg) | 21.1.前前軸重 | ||
| 21.2.前後軸重 | ||||
| 7.自動車の種別 | 21.3.後前軸重 | |||
| 21.4.後後軸重 | ||||
| 8.燃料の種類 | 21.5. 総重量 | |||
| 22.車輪配列 | ||||
| 9.原動機の型式 | 23.最高出力 (kW/rpm) | |||
| 24.最大トルク (N・m/rpm) | ||||
| 10.総排気量(L)又は定格出力(kW) | 25.騒音 | 25.1.規制区分 | ||
| 25.2 近接 (dB/rpm) | ||||
| 11.1.車台番号の打刻様式 | 25.3.定常 (dB(km/h)) | |||
| 25.4.加速 (dB) | ||||
| 11.2.車台番号の打刻位置 | 26.排出ガス値 | 26.1.試験モード | ||
| 26.2.CO( ) | ||||
| 11.3.原動機の型式の打刻様式 | 26.3.HC( ) | |||
| 26.4.NMHC( ) | ||||
| 11.4.原動機の型式の打刻位置 | 26.5.NOx( ) | |||
| 26.6.PM( ) | ||||
| 26.7.PN( ) | ||||
| 27. 燃料消費率 (km/L) | 27.1.JC08 | |||
| 27.2.WLTC | ||||
| 27.3.JH15 | ||||
| 27.4.JH25 | ||||
保安基準 (1節扱い)
R 155 /156も対象?
EVは電費測定が必要?

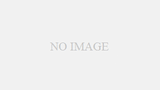
コメント