日本の場合はUN規則+ 日本オリジナルが基準だが、同様にEUはUN規則+ EU directive-> Whole Vehicle Approval.アジア地域もほぼ同じ(UN + Domestic regulationとして)。EUはdirectiveとして、RRRはIMDS reportからRRRの計算を行い、それを認可に入れる。事務作業として時間がかかるのはRRRだと思う(開発という意味ではなく).
EUのケースだと
変更内容の説明、information documentationの記載をもとに、Technical Serviceと試験内容のつめ。並行して、試験自動車の準備。試験自動車の準備が一番時間がかかるような気がする。試験は通常フル項目を行うと2ヶ月程度かかる。その後2weeks程度でWVTA発行。
EUのCoPは初年度がなく、一年後立ち会い、その後1年後に書面審査、の後1年後に書面審査、その後立ち会い試験。スペインの認可機関を使用した例では、その認可機関(国)がTechincal Serviceに依頼して、審査を実施。審査結果を国に返して、CoC Certifificationの延長が可能となる。スペインの休暇などにより時間がかかり、少しCoC Paperが発行できないタイミングあった気が・・・・。Euro Marketのコントロールが必要になり、ちょっと面倒くさくなる。国からはどの程度の従業員数や工場の大きさ、取得した認可、実施したCoPの結果、前回からの指摘に対する対応等々を文章で求められる。
また、ちょっと気がついたのは、日本では完成検査の更新期間については定められていないが、EUでは時期がある。また、当該有効期間については、生産日が起点となる。また、台数ベースではないため、一台とも登録があったりした場合に、当局と意見が割れました。
また、このタイミングとRRRのタイミングが異なり、困惑した思い出があります。
日本の監査間隔については特段定められていない。不正とは関係ないもの、自動織機の不正案件の報告書(P134)においても、
(抜粋)
この点、品質保証部の管理職は、「日本法においては、量産抜き取り検査は、国内認証の申請者が自主的に定めたルールに従って実施することとされていたところ、厳密に検査法に定めた抜き取り頻度を守らなくともよいという意識が品質保証部員には根付いてしまっていたと思われる。」など述べる。
https://www.toyota-shokki.co.jp/news/item/reference_full.pdfわかりやすい

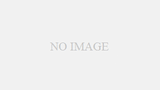
コメント