型式を取得することにより、自社で検査を行える。
車両の申請 + 完成検査
により成立。完成検査は別項目で立てる。
プロセス的には
- 打刻の届出
- 審査部に申し込み (3より1ヶ月前程度)
- 審査部に説明(車両の説明と試験の説明)
- 審査部受け付け(MLIT受け付け)
- 試験
- お金の振り込み(審査部決裁までにMLITへ申請料金。審査部へは受け付けから60日かな?)
- 審査部決裁
- 審査リコール課決裁
*4から8は、標準期間が60日
輸入車であれば、契約していることを証明する必要がある。ただし、独占販売なのかは不明瞭。
自動車の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入することを業とするもの(以下「自動車製作者等」という。)
審査リコール課決裁後に、どこかのタイミングで公示される場合があるので隠したい時はチェック!(新規など)
外国の認定証は、適合されているとみなされるので、試験は関係なし。証明書等を付する。なお、1958協定上受け入れ義務があるので、日本が何かの責任を持つことはなく、指摘はできるものの、受け入れを拒否することはできない。また、当該試験に関する監査(CoP)についても日本は口出しをすることはできない。そのため、認定証を活用することが有用だと思われる。(日本だけが異様に厳しいので、リスク回避)
審査部は認定証をカバーページだけ求める。それは、それ以外を求めるとその責任を負うと考えるのか、単に簡略化だけなのかは不明。
第七十五条
3第一項の規定による指定は、申請に係る自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合し、かつ、当該自動車が均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。この場合において、次条第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部(同項に規定する特定共通構造部をいう。)の当該指定に係る構造、装置及び性能並びに第七十五条の三第一項の規定によりその型式について指定を受けた装置は、保安基準に適合しているものとみなす。
装置の指定)
第七十五条の三
8特定装置のうち国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところによりその型式について外国が行う第一項の規定による指定に相当する認定その他の証明を受けた場合には、第七十五条第三項後段及び前条第三項後段の規定の適用については、第一項の規定によりその型式について指定を受けた装置とみなす。
認可後に、下記の人たちとよく話す必要がある。
JAIA
OSS
任意保険(先んじて調整が必要)
登録
整備(完成検査のため)

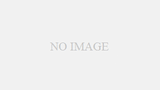
コメント